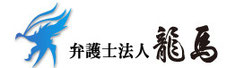元請・下請トラブル - 弁護士法人龍馬 群馬県高崎市・太田市・埼玉県さいたま市・東京都港区
元請・下請トラブル
近時,建設ラッシュに伴う人手不足などにより,従前までは取引関係のなかった業者と取引を行い,取引慣行の違いなどからトラブルに発展するケースが増えています。

1.契約書作成の重要性
下請契約は,契約書を作成しなくても口頭の約束だけで有効に成立します。実際に,建設業界などを中心に契約書が作成されず,口頭だけのやり取りで工事の追加や変更を済ませてしまう場合もあります。
しかし,口頭での約束の場合は,内容が不明確となり,お互いの認識が異なっている場合があり,後日,紛争を引き起こす原因になります。
そこで,できる限り契約書(注文書・請書)を作成し,仕事の内容(範囲)・代金・期限など明確に定めておくことが望ましいといえます。
なお,下請法では,親業者が発注書面を下請事業者に交付することを義務づけています(下請法3条),建設業法においても,法定の事項を記載した請負契約書の作成と交付を義務づけています(建設業法19条)。
2.下請代金支払遅延等防止法(通称,「下請法」)
元請・下請の関係は,立場の優劣があることが多く,元請事業者によって優越的な地位を濫用した行為がなされる場合があります。
そこで,下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まることを目的として規定された特別法が,下請代金支払遅延等防止法です。
元請事業者にとってはコンプライアンスの観点から,下請事業者にとっては救済手段の方法という観点から同法について理解しておく必要があります。
ⅰ 下請法の対象となる取引
製造委託
例えば,電機メーカーが部品の製造を他の事業者に委託する場合
情報成果物委託
例えば,ソフトウェア開発業者が消費者に販売するゲームソフトの作成を他の開発事業者に委託する場合
修理委託
例えば,自動車ディーラーが請け負う自動車修理を修理業者に委託する場合
役務提供委託
運送やビルメンテナンスをはじめ,各種サービスの提供を行う事業者が,請け負った役務の提供を他の事業者に委託することをいいます
ⅱ 下請法の対象となる親事業者・下請事業者の関係
製造委託・修理委託の場合
下請事業者の資本金3億円以下
(個人を含む)
● 親事業者の資本金1千万円超3億円以下→
下請事業者の資本金1千万円以下
(個人を含む)
製造委託・修理委託の場合
下請事業者の資本金5千万円以下
(個人を含む)
● 親事業者の資本金1千万円超→
下請事業者の資本金1千万円以下
(個人を含む)
ⅲ 下請法の定める義務・禁止事項
義務
●書面の作成・保存義務
●下請代金の支払期日を定める義務
●遅延利息の支払い義務

禁止事項
●下請代金の支払遅延の禁止
●下請代金の減額の禁止
●返品の禁止
●買いたたきの禁止
●購入・利用強制の禁止
●報復措置の禁止
●有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
●割引困難な手形の交付の禁止
●不当な経済上の利益の提供要請の禁止
●不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
3.請負代金の回収
特に,請負関係における債権回収の特殊性を指摘すれば,①契約書等が不十分なことが多く,その瑕疵が当事者にとって(多くの場合は請求する側にとって)思わぬ不利益をもたらす場合があること,②仕事の目的が専門的な内容となるため審理などに時間を要する場合が多いということが挙げられます。
請負代金のトラブルについては早期に専門家の助言を求めるべきといえますし,できれば契約書や発注書・請書を作成する段階で専門家の助言を求めるべきといえるでしょう。
また,請負代金の請求にあたっては,民法のみならず,前述下請代金支払遅延防止法などを利用し,公正取引委員会・中小企業庁からの措置請求を求めるべきケースもあります。
4.建設業の方へ
近時,建設ラッシュに伴う人手不足などにより,従前までは取引関係のなかった業者と取引を行い,取引慣行の違いなどからトラブルに発展するケースが増えています。
建設業が伝統的に多層の請負契約関係の構造になっており,また,元請・下請の間においては十分な契約書面を作成していないこともトラブルの要因となっています。
したがって,一度トラブルになった場合(例えば,追加工事代金の価格の認識の違い,工事の遅延の損害賠償負担割合)に,思わぬ出費を免れないケースがあります。
建設業は,下請法の規制対象とはなっていませんが,これは同法とは別に建設業法が存在し,別途規制があるためです。ただし,建設業法は下請保護を第一の目的とはしておらず,実質的に同法による保護は限定的といえるでしょう。