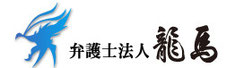終末期医療と自己決定
延命治療を望むか否か,自分がしっかりしているときに自己決定しておくことが,介護する家族の負担を軽減します。できれば,公正証書で,そしてホームロイヤーに事前指示書を作成依頼しておくことができれば,自然の逝き方が可能となるでしょう。

1. 問題の所在
本人の同意がないままされた手術・治療行為は,不法行為であり,違法行為とされる可能性がある。しかし,他方で,保存治療行為にとどめられた結果,高齢者は回復する機会を失ってしまう。高齢者における医療同意の問題は,医的侵襲となる手術・治療行為となる手術・治療行為を行わなければならないのに,判断能力が減退した高齢者本人の意思が不明であるため,医師が手術・治療行為に踏み切れないジレンマが生ずる点にある。
例えば,認知症により徘徊を常習的に行う高齢者が,大腿骨を骨折し,治療には手術が必要になった場合,医師は,積極的に大腿骨骨折手術を行うだろうか。
本人とすれば,手術をして,歩行可能となることが最善の利益であろう。手術による回復後の徘徊への危険性については,別途周辺の配慮で対応すべきである。それゆえ,医療同意があれば,手術に着手する。
しかし,高齢者本人には医療同意能力を認めることができない事例が多い。医療現場において,家族がいれば,家族に医療同意を求めるが,家族がいない場合,成年後見人に同意を求められることもあるが,現行の成年後見制度では,後見人には医療同意権は認められていないため,同意権者は存しないことになる。
また,医師には,大腿骨骨折手術により骨折を治療すれば,本人が再び徘徊を繰り返すことが予見される。徘徊によって,転倒事故を起こせば,本人の生命の危機に繋がることでもある。高齢ゆえ,歩行のためのリハビリが可能のなるのか懸念もある。このような消極的理由から,医療同意なき場合には,保存治療で対応する可能性が高い。
これでは,高齢者の自己決定権としての医療同意を重視することで,患者の医療を受ける権利を失ってしまうという,本末転倒の結果をもたらしてしまう。
2.高齢者の「医療」同意とは…特別の治療の場合
ところで,高齢者が病院に入院する,診察を受けるなどの医療契約を締結する通常の医療の場合には,本人の判断能力が減弱していても,家族や後見人が医療同意することで入院等の契約をすることができる。すなわち,家族の場合は経験則を根拠とし,後見人の場合には,民法858条における身上配慮義務を根拠とする。
高齢者の「医療」同意が問題となるのは,上記の場合ではなく,特別な治療を要する場合である。特別な治療とは,重大な,または持続的な身体の完全性または人格の侵害を通常伴う治療である。つまり,治療による侵襲が重大な場合である。
そして,医療行為についての「同意」は法律行為とはいえないため,その内容や程度は意思能力とは異なる基準で判断される。すなわち医療同意能力は,「その医療行為の侵襲の意味が理解でき,侵襲によってどのような結果が生じるかを判断できる能力」である。この特別の治療が,医療同意能力を有しない高齢者本人に対して行われる場合に問題となる。
3.医療同意が問題となる時期
また,高齢者に対する医療の場合,保存治療で対応する可能性が高いのは,終末期にあたるからだともいえる。
高齢者の終末期には,A. 急性型,B. 亜急性型,C. 慢性型がある。
A .急性型
B.亜急性型
C.慢性型
それゆえ,高齢者の医療同意問題は,C. 慢性型を中心に,意思決定支援の内容を検討する意義がある。
4.成年後見と医療同意
このような慢性型の終末期の場合,高齢者の医療同意の問題について,アメリカ,ドイツ等では身上監護の代表的な手続として,財産行為の代行よりもさらに厳格な要件の下に,同意権限を成年後見人に与えている。
これに対してわが国では,この医療同意問題について社会一般のコンセンサスが得られていないとし,本人の自己決定および基本的人権との抵触等の問題についての検討も未解決である段階で,成年後見の場面についてのみ,これらに関する規定を導入することは,時期尚早であるとして,当面は社会通念のほか,緊急性がある場合には緊急避難・緊急事務管理等の一般法理に委ねざるをえないとされている(「新版注釈民法(25)親族(5)〔改訂版〕400頁」)のである。
- もっとも,「医療行為の同意取得が要請されながら,本人の同意取得について法的規制を欠くために,その要請は満たされておらず,医療現場は混乱している」とし,「これは社会一般のコンセンサスが得られていないことに由来するのではなく,法整備の遅れに由来するのである」と厳しい反論がなされている(新井誠「成年後見と医療行為」日本評論社12頁)。
- ところで,我が国の成年後見制度は,後見人が行うことができるか否かという観点から医療同意権の有無が議論され,本人が医療同意できるか否かという観点の議論が置き去りにされてきた。そのため,高齢者本人が医療同意能力を喪失していることを前提とされ,誰が本人に代わって同意することができるかという問題のみが検討されてきた。これに対し,医療現場においては,高齢者が医療同意できるか否かにつき判断する過程を問題とし,支援の要否,程度,具体的方法を考えるにあたり,本人が困っているのは「何についての決定か」という視点が重要であり,本人を中心として考える成年後見制度を設計すべきであろう(菅富美枝「イギリス成年後見制度にみる自立支援の法理」ミネルヴァ書房54頁)。
例えば,ドイツでは手術・治療行為・その他の医的侵襲に関する重要な決定・同意には裁判所の許可を得ることが義務づけられている(ドイツ民法典1904号)。
5.障害者権利条約
成年後見制度から意思決定支援制度へ向けての流れを作ったのは,障害者権利条約である。日弁連人権擁護大会では,同条約が求めた認知症や障害のある人の自己決定権の実現を目指している。
(1)障害者権利条約
障害者権利条約を,日本は2014年1月20日に批准した。この障害者権利条約第12条は,障害がある人も法律の前に人として認められる権利を有すること,他の者と平等に法的能力を享有するものと認められること,法的能力の行使に当たって必要な支援を利用することができるようにすることを求めている。
つまり,精神上の障害があることによって法的能力を制限し,他の者が代わりに決定することを認めることは,障害があることによる差別にほかならず,個人の尊厳を侵害するものであり否定されなければならない。精神上の障害があっても法的能力の行使にあたってはまず必要な支援がなされるべきであり,他者決定である代理や代行ではなく,意思決定支援の制度に移行しなければならないということを求めている。
(2)成年後見制度から意思決定支援制度への移行
成年後見制度は2000年に施行され,自己決定の尊重を理念として掲げた。しかし,本人意思の尊重を明文化したとはいえ,どのように本人意思を尊重するのかについて,何らの基準や指針を示さず後見人の裁量に委ねてしまい,むしろ保護との調和という趣旨を残したため,後見人は保護の観点に重きを置き,本人意思の尊重は形だけの理念となり,かえって後見人によって自己決定が侵害されている事例さえ見受けられる。
それゆえ,意思決定を自ら行うことができない高齢者のために後見人が行うことができる権限範囲はどこまでかという視点ではなく,意思能力を喪失していく過程にある高齢者本人の意思決定支援を中心とした制度設計が必要である。
すなわち,精神上の障害があることによって,あらゆる事柄について自分で決めることができないというわけではない。ただ,精神上の障害が判断することに影響を及ぼし,自分で決めることに困難を伴うという場合,直ちに誰かが代わりに決めてしまうというのではなく,本人の困難がどこにあり,どのような支援をすればそれを乗り越えられるかを考え,その支援によって自己決定を導き出すことが重要となる。
(3)医療同意問題に関する課題解決の方向性
- 高齢者本人が,判断能力を喪失し,医療同意できない状況であることが明らかであるときに,誰が本人の意思を代弁することができるかという課題が最後まで残る。すなわち,今後,社会の法化,少子高齢化が進むにつれて,法的正当性を有する医療同意権者の存在が必要とされるのである(青木仁美『オーストリアの成年後見法制』357頁(2015年,成文堂))。
ところで,現在,家族の同意によって,医療同意がなされたと認められているが,本人とその家族との間に利益相反があるときには本人の意思を代弁することはできない。すなわち,推定相続人である家族は,常に本人の意思につき,最善の理解者ではない。
また,一方で,任意後見人は本人が証書において指名した者であり,自己決定支援の「最も適切な者」という推定を受ける(選択の契機)が,他方,法定後見人は,本人が「最も適切な者」として選択した者ではない。
さらに,医療同意を必要とする医療現場では,生命それ自体を尊重する価値観から,一分一秒を延命させる医の論理があるため,医療同意の判断者には相応しくない。むしろ,判断能力を喪失した者に対する医療意思決定プロセスに独立した判断機関を設けることにより,関係者がストレスを持たない決定が可能となろう。
意思決定支援制度への移行にあたっては,イギリス2005年意思決定能力法に基づき,医療同意に関して日本においても同一の方向を目指すべきである。
すなわち,上記課題に対して,次の①乃至⑤の回答を導き出すことができる。
①一定の家族に自動的に医療同意権を与えることは出来ない。
②本人が事前に指定した場合には,任意後見人に医療同意権限を与えてよい。
③本人の意思とは無関係に任命される法定後見人に医療同意権を与えるべきではない。
④医療現場の「責任ある裁量権」に任せるべきではない。
⑤独立機関(保護裁判所)を設けて限定的に医療同意権を与えることができる。
6.立法化に向けて
医療同意における立法化を検討していくにあたり,患者の医療行為に対する同意能力につき意思決定支援過程を確立した上で,医療に関する同意能力が完全に喪失していると決定された高齢者に代わって,医療同意を行う代行者を決定していくべきである。
医療同意に関する立法化の提案となる日本弁護士連合会『患者の権利法大綱案』について該当条項を掲示する。
(1)患者の自己決定権(『患者の権利法大綱案2-2-1』)
②患者は,前項に自己決定のための必要な援助を受けることができる
日弁連は,判断能力が減弱した高齢者について成年後見制度から意思決定支援制度へと大きく舵を切った。高齢者が精神上の障害があることによって,医療行為について自分で決めることができないというわけではない。ただ,精神上の障害が判断することに影響を及ぼし,自分で決めることに困難を伴う場合が生じるだけである。その際,どのような支援をすれば医療行為を理解し,同意し,選択し,拒否する判断が出来るかを考え,その支援によって自己決定を導き出すことが重要となる。
それゆえ,患者の自己決定権と,自己決定のための必要な援助を受けることができる(『患者の権利法大綱案2-2-1』)ことを明記した条項は,意思決定支援制度を表したものとして受容できるであろう。
(2)判断能力が欠ける患者(『患者の権利法大綱案2-2-2』)
①患者に医療行為に関する説明を理解した上で,当該医療行為につき同意,選択又は拒否する能力が欠如している場合は,原則として,患者の家族その他患者を保護する者(以下「家族等」という。)が当該医療行為につき同意し,選択し,又は拒否することができる。
②前項の場合であっても,患者の家族等並びに医師及びその他の医療従事者は,患者の能力に応じて,患者をその意思決定の過程に関与させなければならない。
意思決定支援の考え方からすれば,判断能力が欠ける患者の場合,患者の家族等に同意を求める条項案(『患者の権利法大綱案2-2-2』)には躊躇を覚える。医療行為に対する同意は一身専属性を有し,たとえ家族であろうと代行することはできない。ましてや,配偶者や子といえども本人と何年も交流がない場合もあり,家族というだけで当然に医療同意権を認めることはできない。本人の意思をもっとも知り得,本人にとっての最善の利益を図りうる立場にある家族だからこそ,同意の代行が許されるにすぎない。本条項案第1項「患者の家族その他患者を保護する者」として,医療,介護,ケアを介して本人に関わる人々に拡大したのもまた,本人が意思決定能力を有していたらそのように望んだであろう」決定に資するからであろう。
また,本条項案第2項において「患者の能力に応じて,患者を意思決定の過程に関与させなければならない。」と規定することも,意思決定支援の考え方からすれば当然であろう。
いずれにしろ,「家族の変容」が押し寄せている現状において,一定の家族に自動的に医療同意権を与えることはできない。
7.「今」備えておけること
(1)任意後見契約の締結と事前指示書の作成
任意後見人は,判断能力が困難・喪失してしまった時に,本人に代わって財産管理,生活の支援をする。任意後見契約の際,医療契約は,代理権を付与する委任事項に含まれるが,医的侵襲行為に対する同意は,法的後見制度と同様,任意後見人の権限は及ばず,委任事項とならない。しかし,任意後見契約の締結においては,「受任者を信頼し,任せる」ことに対する積極的理解が求められ,相手が信頼するに足る人物かについての判断であるべきである。だからこそ,任意後見人の選任をすることにより,事前指示書に基づく個別医療を受けるか否かにつき,意思を反映させることが必要である。
(2)事前指示書
事前指示書は,延命治療を拒絶するなどの書面による医療行為に対する自己決定書面である。事前指示書とは,リビング・ウィル(尊厳死宣言)とほぼ同じ意味に用いられるが,事前指示は,終末期だけに限定せず,より長い期間の広い範囲の医療に対する希望を指示することができる。また判断能力を喪失した場合には,自分の望む治療を受けるために,誰に後見人になってもらうかを指定するのである。
オーストラリアでは,病院,介護施設への入所時,後見人と事前指示書を指定または用意することが,法律によって定められている。
ドイツでは,2009年9月1日施行の第3次世話法改正で,「患者事前指示法」が制定され,患者が意思能力を喪失した場合に備えた医療に関する患者の事前指示(リビング・ウィル)に法的拘束力を認めた。
(3)事前指示書には法的拘束力がない
しかし,日本では,事前指示書に法的拘束力はなく,事実上,医療関係者に尊重されるにとどまっている。それゆえ,事前指示書だけではなく,任意後見人による代行判断を合わせることで,本人が自己決定した意思が,判断能力を喪失した時の医療同意の際に実行されることになる。
(4)今,判断しておくこと
患者の権利を保障するには,インフォームド・コンセントを十分に実践し,高齢者,障がい者に対する自己決定や意思表明のための支援が必要である。その実践として,今ある仕組みである任意後見を活用し,事前指示書を普及させることである。
その際留意すべき点がある。任意後見人は,任意後見契約時・事前指示書作成時の条項や内容ではなく,「今」,判断しなければならない医療行為であって,「最善の利益」として現時点推測される本人の意思を医療関係者に伝えていくということである。
医療における意思決定への支援 ~法の知識を持って~
1 川崎協同病院事件
2 終末期医療をめぐる法的問題~安楽死・尊厳死
第2 終末期の三類型
急性型・亜急性型・慢性型
第3 医療における意思決定について
1 本人の意思決定・・・事前指示書
2 家族の同意
3 問題事例の解決・・・大綱案とガイドライン